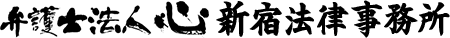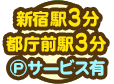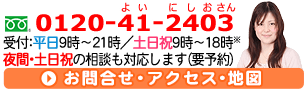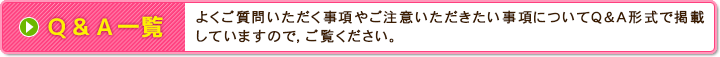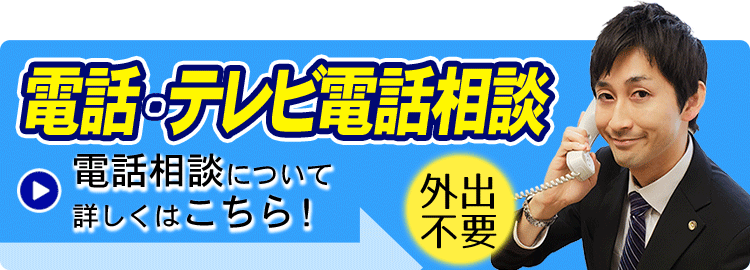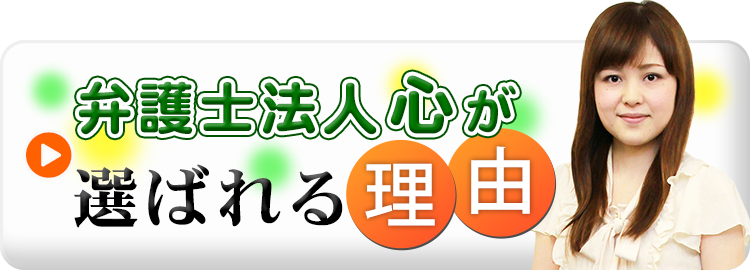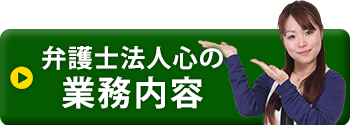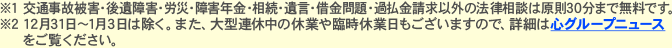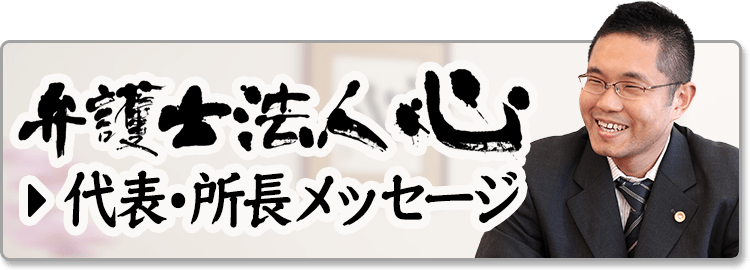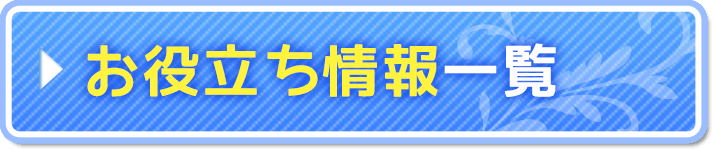疎遠な相続人と遺産分割をする際の注意点
1 誰が相続人なのかを正確に把握するようにしましょう
亡くなった方の財産は、いったん、相続人全員の共有となり、この共有状態を解消するためには、遺産分割協議によって、誰が何を相続するかを決定する必要があります。
この遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立するため、相続人が一人でも欠けると無効となり、やり直しとなってしまいます。
誰が相続人となるのかは法律で決まっており、配偶者や子、両親、兄弟姉妹が主な相続人です。
これらの相続人の中に、まったく連絡を取っていない人だったり、前婚の子などが含まれていたりすると、関係が疎遠になっていることがあります。
そのようなときには、相続人全員を正確に把握することが難しい場合があります。
しかし上述のとおり、疎遠な相続人がいる場合であっても、全員が遺産分割協議に参加しなければならないので、まずは誰が相続人になるのかを正確に把握するようにしましょう。
誰が相続人になるのかは、必要な戸籍を収集したうえで、調査を行っていきます。
2 遺産分割協議の内容を理解したうえで合意をするようにしましょう
遺産分割協議を有効に成立させるためには、相続人全員が、協議の内容をしっかりと理解したうえで合意をすることが大切です。
というのも、遺産分割協議は、亡くなった方の財産を隠して進めたり、相続人が分割の内容について大きな勘違いをしていたりすると、やり直すことになる場合があるからです。
疎遠な相続人と遺産分割をする場合、できるだけ早く終わらせたい方や、不仲を理由にして対面での協議を避けたいと思う方もいるでしょう。
遺産分割協議は、必ずしも対面でする必要はなく、手紙やメールですることもできますが、このような方法だと、対面よりも、それぞれの認識の違いに気づきにくく、後でトラブルになるおそれがありますので、十分に注意をしながら進める必要があります。
協議のやり直しとならないためには、それぞれの協議の手段に応じて、相続人全員が相続財産などを把握したうえで、協議の内容をしっかりと理解することが大切です。
3 専門家へ相談して進めるようにしましょう
遺産分割がまとまると、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印をします。
この遺産分割協議書は専門家でなくても作成することができますが、内容に不備があると、相続手続きが進められず、作成をし直すことになってしまいます。
その際、疎遠な相続人との間ではトラブルになってしまうかもしれません。
そのような事態を避けるために、遺産分割協議書の作成についても専門家に相談して進めるようにしましょう。
また、遺産分割協議においては、協議書を作成する以外にも、相続人や相続財産の調査、相続人間での協議など、やらなければならないことがたくさんありますし、それぞれについての進め方で注意しなければならないことも多くあります。
遺産分割協議を円滑に進めるために、弁護士等の専門家へ相談されることをおすすめします。